コラム
DXの親和性の高い事業とは?導入事例を元に分かりやすく解説
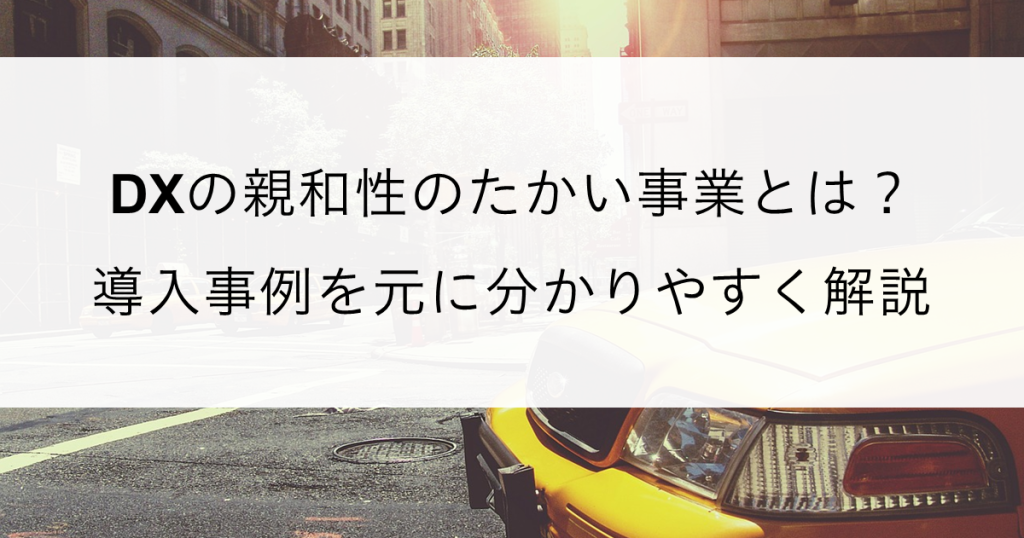
DXに取り組む企業が増える一方で、「自社の事業にデジタル化できるのか」と考える企業もあるかもしれません。デジタル化が向いていない事業は、あるのでしょうか。反対に、DXと親和性が高い事業とは、どんな事業なのでしょうか。この記事では具体的な導入事例を挙げながら、DXと親和性の高い事業について解説していきます。
目次
DXと親和性の高い事業はあるのか
これまでアナログな手法で経営を成功させてきた企業では、自社事業にDXはなじまないと感じるかもしれません。DXと親和性が高い事業、または低い事業は明確に区別できるのでしょうか。
結論からいえば、DXと親和性が低い事業はありません。どんな事業でもDXに取り組む意義は大いにあるのです。
そういえる理由として以下が挙げられます。
- 「DX=IT化」ではないから
混同されがちですが、DXとIT化はイコールではありません。
DXとはデジタル技術とデータを活用してビジネスモデルや組織文化に変革や競争優位性をもたらす取り組みであり、単に業務にデジタルツールを導入することとは異なります。
デジタルツールの導入だけであれば、デジタル関連商品やサービスを扱う事業との親和性が高いといえるかもしれません。
しかし、DXでの最終的なゴールは「ビジネスモデルや組織の変革や競争優位性を作ること」であり、デジタルツールはその手段に過ぎません。
事業内容にデジタルの要素があるかどうかはDX導入に無関係であり、今後も競争力を向上させていきたい企業にとってはDX推進は必須の取り組みといえるでしょう。
- データ重視の意思決定で生産性向上につながるから
経営では「新事業を始める」「既存事業をやめる」「人員を増やす・減らす」といった重要な意思決定を多く行います。
ここで誤った判断をすると損失が出るリスクがあるため、意思決定はできるだけ正確に行わなければなりません。
しかし、従来多くの企業では重要な意思決定が「人間の経験や勘」に頼って行われ、判断を誤ることも多くありました。そこでデータに基づいた意思決定が重視されるようになってきたのです。
データに基づいて判断することをデータドリブンといい、SSRN(Social Science Research Network)の論文では、データドリブンな意思決定を行なう企業ではそうでない企業に比べて生産性が5~6%高いと報告されています。
これは特定の事業に限った話ではありません。どんな事業内容でも意思決定は必ず伴うという観点から、DXを導入しデータを活用することで生産性向上が期待できるといえます。
- 新市場を開拓できる可能性があるから
IT技術の進歩や感染症の流行で市場環境が激しく変化する中、既存事業の展開のみで今後も安定した経営を続けられる保証はありません。
これまでのやり方に固執せず、自社の強みを発揮できる新市場を絶えず探っていく必要があります。そしてDXの導入は新市場参入のための大きな武器となります。
どんな事業内容でも、視野を広げてみればDXを導入することで新たに挑戦できることが見つかるはずです。
DX導入事例
DX導入により事業を大きく成長させた事例を紹介します。
タクシー業界のアナログなオペレーションが一変
株式会社Mobility Technologiesではタクシー配車アプリ『GO』を展開することで、これまでのタクシー業界のあり方を一変させました。
従来タクシーを利用するには「タクシー乗り場に並ぶ」「路上で呼び止める」「コールセンターに電話して配車してもらう」方法がとられてきました。しかしこの方法ではすぐにタクシーがつかまらなかったり、コールセンターになかなかつながらないといった課題がありました。
この状況が、アプリの登場で一変しました。
アプリで位置情報を入力することで短時間でタクシーを呼べるようになり、お客にとっては「必要なときにすぐにタクシーに乗れる」、乗務員にとっては「確実にお客を乗せられる」というメリットが生まれました。
この取り組みのメリットは、単に早くタクシーを呼べるというだけではありません。「どんなお客が・どこで・どの時間に」乗車したかのデータが収集・蓄積されるようになったのです。
タクシー配車の需要予測にはお客の乗車情報を分析することが非常に重要ですが、従来の「乗務員が経験と勘に頼ってタクシーを走らせ客を見つける」手法では、データは蓄積できませんでした。
アプリ経由でタクシーが依頼されることで乗車データは次々と蓄積され、データが溜まるほど予測精度は上がっていきます。
現在同社では蓄積されたデータを活用してAIによる需要予測を行っており、従来の10倍以上の依頼に対応できるようになりました。
タクシー広告のあり方を変えた
Mobility Technologiesの子会社であるIRISでは、これまで紙ベースだったタクシー広告の世界にDXを導入し、広告のあり方を大きく変えました。
これまでタクシー広告といえば後部座席にセッティングされたチラシが主流で、内容は体型の悩みや経済力といった人間のコンプレックスにアプローチするものが中心でした。
IRISでは「タクシー利用者には富裕層や投資家が多い」というデータに注目し、こうした広告内容を一新。より利用者に効果的に働きかけられるようBtoB向けの広告にシフトし、紙媒体だった広告を動画広告に切り替えました。
この取り組みはこれまでのタクシー広告のイメージを一新させ、現在はスタートアップ企業のアピールの場としても活用されています。
DXの導入で新市場を開拓
Mobility Technologies社では、『GO』が浸透してからもコールセンター経由の依頼は減っていないといいます。つまり従来の電話利用による売上はキープしたまま、『GO』利用者分の売上が増加したことになります。
DXの導入により新市場の開拓に成功した好例といえるでしょう。
また同社ではタクシーを利用したフードデリバリー専用アプリ『GO DINE』の展開も開始しています。
配達にはタクシーを利用するため人員や移動手段の開拓はゼロ。利用者や飲食店は既に『GO』を利用している人が多いため、アプリを利用したサービスも抵抗なく受け入れやすいといいます。
この取り組みも、『GO』アプリが実現した先に花開いたものであり、DX実現により新市場を開拓できたといえます。
長年「経験と勘」「電話と無線」で成り立ってきたタクシー業界は、一見DXとの親和性は高くないように思えます。
しかし顧客の利便性や業界の将来性を考えてDXを実現したことで、同社は自社事業のみならず業界全体にも大きな変革をもたらしたのです。
DXは事業の区別なく行われるべきもの
IPA(独立行政法人情報処理推進機構)の発表した「DX推進指標 自己診断結果分析レポート(2020年度版)」では、DX推進指標自己診断で回答し分析対象となった企業305社の業種が公表されています。
305社のうち「製造業(機器)」が21.0%、「製造業(素材)」が17.7%、「情報通信業」が12.1%、「卸業・小売業」が11.1%、「サービス業」が6.9%、「建設業」が5.6%、「金融業・保険業」が5.2%となっており、製造業の割合が多いものの、多業種でDXの取り組みが行われたことがわかります。
また同レポートの2019年度版と比較すると、ほとんどの業種でレポート提出社数が増えています。DXに挑戦する企業は事業内容に関係なく増加しているのです。
もはやDXとの親和性は事業内容の如何によって決まるものではありません。事業の壁にとらわれず、自社でできるDXの取り組みを見極めた企業が大きな成長を遂げていくことでしょう。
データ分析や活用、DX推進に関するお悩み、弊社製品の機能についてご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。
