コラム
DXツールの導入で気をつけるべきポイントとは?
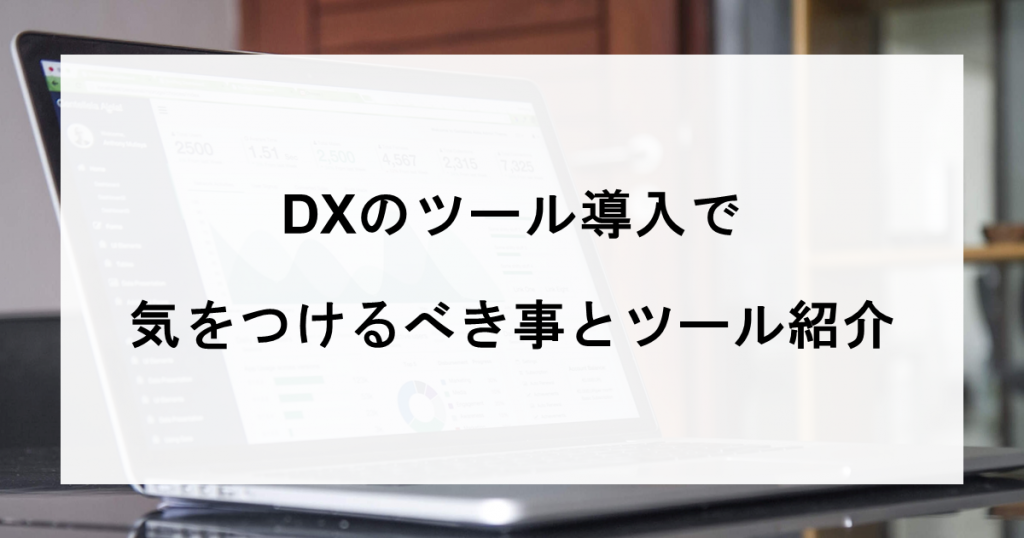
ビジネス環境の激しい変化に対応するため、データとデジタル技術を活用して業務や組織、ビジネスモデルなどを変革し、競争上の優位性を確立するDX(デジタルトランスフォーメーション)。「DX」とだけ聞くと、「難しいのではないか」「何から手を付けたらいいのか」と考える人もいるでしょう。DXを実現する1つの方法として、自社でDXを推進するために適したツールを導入するという手段が挙げられます。この記事では、DXツールを導入する際気をつけるべきポイントや、DXツールの主な種類を紹介します。
目次
DXツールとは
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術やデータを活用することで企業のビジネスモデルや業務、組織の変革を行う取り組みを指します。
DXはIT化と混同されやすい概念ですが、両者は大きく異なります。DXはデジタル技術などを使って人々の生活や企業活動に変革を促す「概念」であり、IT(インフォメーションテクノロジー:情報技術)はコンピュータとインターネットを利用した「技術」のことをいいます。
IT技術はDX推進の手段として用いられることがあります。こうした、DXの手段として用いられるツールがDXツールです。
DXツールには、オンライン会議ツールやチャットツールなどのコミュニケーションツールをはじめ、営業やマーケティングなど特定の業務をサポートする支援ツールなど、さまざまな種類があります。
DXツールの種類
DXツールには、次のような種類があります。
データベース言語の知識を持った人が扱えるDXツール
SQLなど何かしらのデータベース言語が扱える社員がいるなら、データベース言語を用いて操作するツールを導入するのもひとつの手段です。
データを集計して何らかの結果を得たい場合、社内の本番環境とは別に分析環境を用意し、そこにブラウザからアクセスしてコマンドを入力することで必要なデータを取得することができます。
この方法だと、データへのアクセシビリティだけでなく、コマンドを使ってさまざまな業務に対応することが可能となります。また、社内の人材がコマンドを覚え操作に慣れれば、生産性を向上させることができます。
この場合、DXツールの導入だけでなく、社内でDXツールを扱える人材を教育する必要があります。柔軟性が高く生産性も向上するというメリットがある一方で、社員の中にはハードルの高さを感じる人も出てくるため、ユーザー層が広がりにくいというデメリットもあります。
DXツールへの投資の1つの方法として、データベース言語を扱える社員を社内に育てるという方法があります。
ノーコードベースのDXツール
DXツールには、自分たちでコードを書かなくてもいい、いわゆるノーコードで開発できるツールがあります。たとえば、ETLと呼ばれるツールもその一つです。
ETLツールは、データを抽出(Extract)し、適切なフォーマットに変換(Transform)して、格納先であるDWHに書き出す(Load)というもの。
ETLツールはデータを抜き出す操作をグラフィカルに行うことができます。一定の条件のもとデータにアクセスし、その中からどれを抜き出すかといった一連の動作を、アイコンをクリックしていくことで実装します。
プログラミングの知識がない人でも感覚的に操作できるため、ツールを扱うハードルの低さはありますが、一方で、複雑なタスクには向かないといったデメリットがあります。
これはたとえば、MA(マーケティングオートメーション)のように、何らかの条件を満たしている人のデータを抽出して、その人にDMを送るような単純な作業には適していますが、作業の複雑性が上がるほどクリックしなければいけない回数が増えていくため、社内でトレーニングをしてコマンドを扱える人材を育てたほうが業務効率が上がる場合もあります。
業務をすべて自動化するDXツールを作成する
毎回同じ条件でデータを抽出して同じ処理をするのであれば、一連の流れを自動化してしまうのも1つの方法です。
システムを構築するには社内のIT人材がいちいちプログラムを書いたり、ETLツールを使ったりする必要がありますが、業務を自動化することで、ITが苦手なユーザーでも膨大なデータの中からほしい情報をリストにして取り出すことができます。
作業手順を自動化すれば、手間やIT教育の手間なしで誰もがデータを抽出できるようになる一方で、イレギュラーなタスクが発生したときの柔軟性は犠牲になります。自動化ツールを取り入れる場合には、どんな人たちがどんな環境で使用するか、その作業は自動化するのに適しているかを考えることが大切です。
DXツールの選定で気をつけるべきポイント
DXツールを選定する際、どんな点に気をつければよいのでしょうか。
ツールを使う人たちのリテラシーを考慮する
DXツールは、導入すれば直ちにビジネス課題が解決するものではありません。DXを推進する際には、現場で業務に携わる人、業務の意思決定をする人、システムを支える人など、社内のプレイヤーたちがどれくらいのリテラシーを持っていて、どういったソースであれば関係者に無理なく受け入れられるかを考慮する必要があります。
ユーザーの要望を把握する
企業のIT投資では、システムの「機能」に着目しがちです。ツールを導入する際、情報システム部門などが機能の比較表を見たときに、「さまざまなことができる柔軟性」で選定しがちですが、ツールを利用する現場のユーザーは必ずしもそうとは限りません。
現場はどんな課題を抱えているかを考慮せず、不要な機能まで追加してしまうと、次のような弊害が起こります・
・機能がきちんと整理されていなかったり、操作が複雑になってしまったりして、UIがよくなく使いずらい。
・使う機能が特定のものに限られ、ほとんどの機能が使われない。
こういったことを防ぐため、現場ではどんなビジネス課題を抱えているか、その課題を解決するためにユーザーがどんな機能を欲しているか、対象者にヒアリングするなどして要望を把握するように努めましょう。
場合によってはありもののツールを導入するのではなく、できれば自分たちでプログラムを書いて作ったシステムをベースにUIを設計し直たほうが、中長期的に見たら業務にマッチすることもあります。
システムは作って終わりではない
システムを作ったからといって、そこで終わりではありません。業務にあうようツールを作り込んでも、使っている中で業務プロセスが変わることもあります。そうした場合、システムをアップデートするなど見直しは常に生じます。
システムのフロントエンド部分を外注している場合、アップデートのたびに時間とコストがかかります。DXツールを導入する場合は、システムをメンテナンスできる人材が内部にいたほうが、コストやスピード感の点でメリットを感じられるでしょう。
また、データの構造自体を見直すことで業務効率化につながることもあります。作って終わりではなく、常に試行錯誤を続けてシステムを維持し続けることが大切です
DXツールでビジネスの課題を解決しよう
「購買意欲の高そうな営業先を抽出したい」「新製品の開発に消費者の声を活かしたい」。こうしたシーンでDXツールを活用することで、データに基づいた意思決定が可能となり、業務効率化や生産性の向上につながります。
とはいえ、さまざまな機能が実装されたツールが一番よいというわけではありません。解決したい課題や活用する側のリテラシーなどから、自社にあったDXツールを選定しましょう。
データ分析や活用、DX推進に関するお悩み、弊社製品の機能についてご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。
